データサイエンティストの業務内容や働き方の実情を、多くの人に正しく知ってもらいたいと考え、企画を始めたインタビューシリーズ。
第五弾の後編は、引き続き大同生命保険株式会社 システム開発二部でデータサイエンティストをされている、上田知展さんにお話を伺います。
−現部署の在籍人数を教えてください。また新入社員や中途採用、上田さんのように他部署から転籍する方はいらっしゃいますか?
上田さん: デジタル推進課は現在、約20名在籍しています。新入社員は私の代では1名だけでしたが、2022年以降は毎年2名ずつ配属されています。
転籍はデジタル推進課自体が元々T&D情報システム株式会社にあった部署なので、全員が一括で転籍する形でした。他には、主に保険数理のプロであるアクチュアリーの方が部署異動という形で配属されています。
−上田さんには後輩がいらっしゃるのでしょうか?
上田さん: はい。10人近くの後輩がおり、いずれも入社後すぐにデジタル推進課に配属されたメンバーです。
データ分析業務は、基本的に1案件2〜3名で進めています。メインの担当者1人に対して、新入社員がサポートの役割として参画し、業務を学んでもらっています。
OJT制度を導入している配属1年目の後輩だけでなく、実務を通じて後輩の育成を行っていますね。
−給与に関して教えてください。
デジタル推進課はシステム部門に属しているのですが、システム部門の初任給は年々上がっていっています。参考までにシステム部門における2026年度入社の大学卒の初任給は28万円を予定しています。
−昇給の頻度はいかがでしょうか。
上田さん: 昇給は年に1回ですが、だいたい4年目、7, 8年目で昇格した際にガツンと上がります。年間での評価はもちろん、昇格が年収に大きく影響します。先輩から話を聞く限り、他の金融機関と比べると、昇給ペースは早いようです。毎年、年度始めに目標設定を行い、中間面談を経て、3月末に目標達成状況を上司と擦り合わせます。基本的には、実績に伴って昇給する仕組みです。また、役職が上がることや職務が変わることでも昇給の機会がありますが、タイミングとしては年1回の昇給が基本です。
−現在の収入に対する満足度はどのくらいですか?仕事内容と合わせて、率直な感想をお聞かせください。
上田さん: 100点満点中で言えば、90点くらいです。基本的には一般的な金融業界の平均程度の収入を頂いているので満足しています。
−入社される前から、データサイエンスについて一通りのスキルや業界の知識を身につけていたと思いますが、入社後さらに向上したスキルはありますか?
上田さん: データサイエンティストに求められる「データサイエンス力」「データエンジニアリング力」「ビジネス力」の3つで言うと「ビジネス力」が最も向上したと感じています。
データサイエンス力やデータエンジニアリング力に関しては、社内で使用するツールや手法がある程度決まっているので、大学時代と比べて特に難しいことをしているという感覚はありません。
一方で、ビジネス力に関しては入社後非常に苦労しました。特に保険業界の業務知識は複雑ですし、学生時代にはあまり学べなかった対人コミュニケーションやプロジェクトマネジメントのスキルが今では身についたと感じています。
−やはり、ビジネスのキャッチアップに苦労されたということですね。特に苦労したエピソードがあれば教えてください。
上田さん: 先ほどお話しした医務査定AIの査定ルールの部分です。
当社では、できるだけお客さまのご契約をお引き受けできるように、他の保険会社に比べて丁寧に査定を行っています。その反面、複雑なルールとなっていて、理解するのに非常に苦労しました。
確認や整理のために他部署の方に「この理解で合っていますか?」と相談したり、前任で保守メンテナンスを担当されていた方にお話を伺ったりしながら、少しずつ解決をしていきました。
また急ぎでない場合でも、ナレッジとして蓄積しておくために社内資料を確認するようにしていました。
−他の部署や役職・役割が異なる方々とのコミュニケーションは難しいと思いますが、いかがでしたか?
上田さん: 最初は少し緊張しました。特に協働する本社部門の相手が課長などの場合が多く、2年目の私は苦戦することがありました。しかし最近では、課内でのやり取りと同じように、気軽に質問ができるようになりました。
これは、大同生命に転籍してフリーアドレスの環境に慣れてきたことも要因の一つです。様々な部署の方が隣に座っている環境なので、コミュニケーションが取りやすくなっています。

−なるほど、そういったコミュニケーション環境で仕事ができているということですね。今後は、どのようにビジネススキルを伸ばしていきたいとお考えですか?
上田さん: データ分析にはある程度慣れてきましたが、その先の課題を解決するための施策について、マーケティングや経営学の基礎的な知識がもう少しあれば、より価値ある提案に繋げられると感じています。
プロジェクトマネジメントやビジネスコミュニケーションのスキルは伸びてきたと実感していますが、今後はデータ分析の結果を具体的な施策に落とし込み、会社の方針に合った提案を行うための、コンサルティング寄りのビジネススキルが求められていると感じています。
−現在5年目ということですが、入社から現在までの成長をどのように感じていますか?
上田さん: 成長の実感はありますが、他の人に比べるとスピードとしては特に速くはなかったと思います。壁に何度もぶつかりながら、1つ1つ正面から突破してきたような感覚です。1つ下の後輩が非常に優秀で、彼と比べると自分の成長スピードは特別速いとは言えないと感じています。
−後輩にライバルがいるというのも、良い環境ですね。スキルに関しては、何か資格を取得されたりしていますか?社内で必要になるものや個人的に取得されたものがあれば教えてください。
上田さん: 最近は会社から求められる資格が多いので、それがメインになっています。例えば、生命保険の営業は直接行いませんが、営業の方と同じような資格を取得することがシステム部全体でも推奨されています。
また、システム部門で働く以上、応用情報技術者試験を受けたりしています。その合間にデータサイエンティスト検定リテラシーレベル(以下、DS検定★)も取得しました。
−DS検定★の難易度はどのように感じましたか?
上田さん: 大学でデータサイエンスを学んでいたので、基本的な部分は特別な学習をする必要もなく、復習のような感覚で取り組めました。
ただし、コンプライアンス関連や画像処理などの専門的な手法については大学ではあまり学んでおらず少し勉強が必要でしたが、専門分野を押さえつつ、他の知識も補うことができたので、改めて学ぶ機会になったと思います。
質問の回答とは異なりますが、当社ではDS検定★を応用してデータサイエンティスト育成に役立てています。例えば社内でデータサイエンティスト育成の認定試験を作る際に、DS検定★を参考にしています。この検定を受けることで、必要な知識を効果的にピックアップできています。
−社内のDS検定★の認知度や受講率はどのような状況ですか?
上田さん: 認知度は高いのですが、受講率はあまり高くないように感じています。データサイエンティストが約15名いる中で、現在資格を持っているのはおよそ5人くらいです。
−今後、後輩にもこの資格を勧めたいと思いますか?
上田さん: そうですね、できれば受験して資格を取得してもらいたいと思います。社内で働きかけをしていき、後輩たちが学びやすい環境を作っていきたいですね。
−改めて会社の主力商品についてお伺いします。
上田さん: はい。創業当初から中小企業向けの保障を提供してきましたが、最近では中小企業の課題解決への伴走支援にも力を入れています。例えば、『健康経営』というワードが最近注目されていますが、中小企業の従業員が長く働き続けられるように支援するサービスを提供しています。
また、中小企業の経営者同士が気軽に相談し合えるコミュニティを作る『どうだい?』という経営支援サービスにも注力しています。デジタル推進課で経営支援サービスや『どうだい?』の分析を行っているため、必要に応じて私もサポートに入っています。
−データサイエンス職の社内での評価や待遇について、どのように感じていますか?
上田さん: 社内での待遇については、非常に良くしていただいていると感じています。満足度で言えば、100点中80点くらいです。
社内には、他にも保険数理のスペシャリストなどがいますが、彼らと同じように扱っていただいている点で、良い意味で特別扱いされていないのが良いと思っています。
ただ、残りの20点は、社内でのデータサイエンティストの認知度がまだ低いと感じており、そこが課題と感じています。
先述の『どうだい?』というサービスの開発・運営チームとも関わりを持つことで、部署全体としては徐々にデータサイエンティストの認知が広がってきているとは感じています。
ただ個人的には「データサイエンティストがいる」というだけで終わらせたくはなく、社内で「こういう成果を出しました」と大々的に報告できる場が設けられると、さらに良い環境になるのではないかと考えています。
−仮に上田さんが新卒に戻ったとして、就職活動を行うとしたら、どのような会社を選びたいですか?
上田さん: おそらく今と同じように事業会社を選ぶと思います。入社した会社で、自分ができることを考えて何かを成し遂げたいという気持ちが強いので、同じような選択をすると思いますね。
例えば、今であれば中小企業向けの経営支援サービスに注力したいです。昨今の中小企業の経営者に対するデータやアンケート調査を見ると、人材不足や1人当たりの生産性の低さが課題として挙げられています。そうした企業を支援し、データサイエンスやDXの取り組みを推進することで、経営を支援したいと思っています。また、データサイエンティスト協会の学生委員会に所属し、日本国内のデータサイエンティストの人口を増やすことにも貢献したいと考えています。
−現職場での人間関係について教えてください。
上田さん: 人間関係は非常に良好です。学閥もありませんし、システム部門の若手で飲み会を開くなど仲が良いです。フリーアドレスの制度もあり、他部署の人とも距離が近くなり、挨拶を交わす機会も増えています。人間関係については全く不満がありません。
−リモートワークの導入状況や柔軟な働き方についても教えてください。
上田さん: リモートワークの環境はすでに全社員に整備されていて、家で仕事をすることも可能です。実際には皆、週に2〜3日程度は在宅勤務をしています。
ただ、私は他部署の方と話すのが最近楽しいと感じるのと、出社した方が仕事の進みが早いので、基本的に出社するようにしています。
−他にも共通の趣味を持った社員同士で、休みの日や仕事帰りに集まるようなサークル活動はありますか?
上田さん: 私の代では主に金曜日に飲みに行くことが多いですが、後輩たちはダーツにハマっていて、みんなで行っているみたいですね。

−会社について、良かったところや悪かったところをそれぞれ教えてください。
上田さん: 良かった点は、人材育成やキャリア支援がしっかりしているところです。資格を取得すると昇格に繋がったり、奨励金が出たりと、人材育成に力を入れています。試験が多すぎると感じる人もいるかもしれませんが、育成の面では非常に充実しています。
気になる点としては、金融業界特有の堅さがあり、スピード感が出にくいと感じます。もちろん、お客さまのお金を預かる以上、一定の慎重さは必要だとも理解していますが、他の業界と比べると、時間がかかることが多いです。一方、このような課題を解決していくための議論もされており、今後は徐々に解消に向かうだろうと思っています。
−データサイエンティストを目指す方々に、伝えたいメッセージがあればお願いします。
上田さん: 今後、データサイエンスのスキルはデータサイエンティストに限らず、様々な職種で求められるようになると考えています。その中で、データサイエンス学部の学生たちの価値はますます高まると思います。しっかりと勉強し、実践経験を積むことで、ビジネスで存在感を発揮できる人材になってほしいと思います。私も、データサイエンティスト協会を通じて学生支援を推進していきたいと考えています。

インタビュー:
データサイエンティスト協会 企画委員会
株式会社分析屋 野口
株式会社GRI 小林
ライター:
株式会社BICP DATA 山田
株式会社Hi-Lights 清水
- カテゴリ
-
-
DS関連NEWS
-
インタビュー
-
スキルアップ
-
コラム
-
教えて!DS
-
- アーカイブ
-
-
2026年
-
2025年
-
2024年
-
2023年
-
2022年
-
2021年
-
2020年
-
2019年
-
2018年
-
2017年
-
2016年
-
- 記事アクセスランキング
-
- タグ

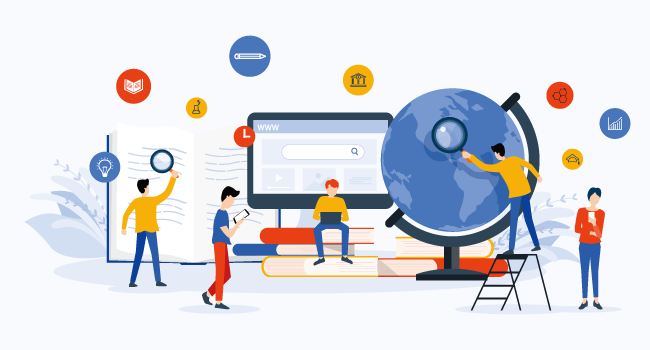





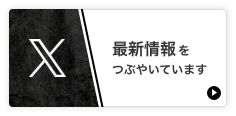
大同生命保険株式会社
上田知展 氏(26歳)
データサイエンティスト歴5年目・システム開発二部 デジタル推進課
※企業の採用情報はこちら