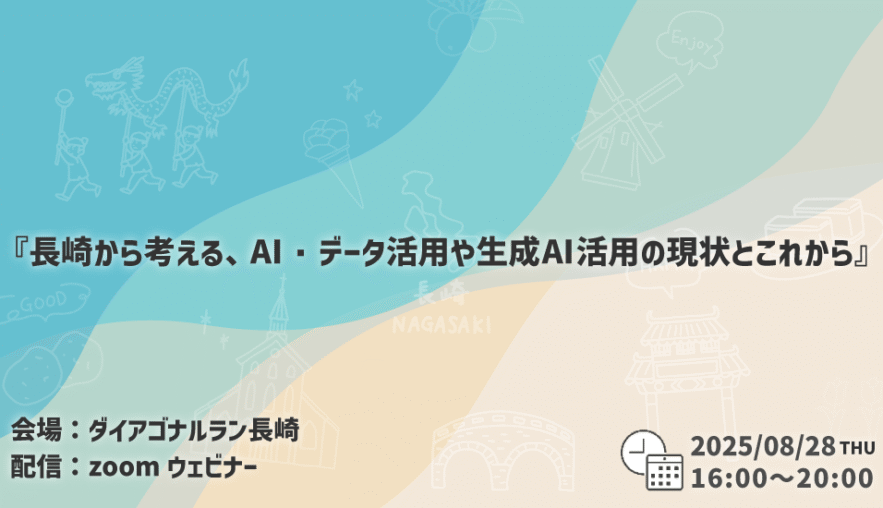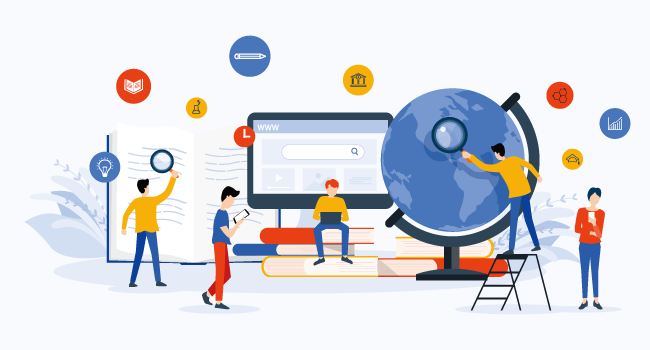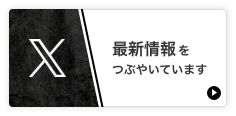データサイエンティスト協会 九州支部は、2025/08/28(木)に「長崎から考える、AI・データ活用や生成AI活用の現状とこれから」と題したイベントを開催しました。会場はダイアゴナルラン長崎で、オンライン配信も同時に行われました。
このイベントは、地方でのデータサイエンス普及と活用促進を目的とし、長崎の実践的視点からAI・データ活用の現状と可能性を探るものです。生成AIなどの先端技術の活用事例を多角的に検証し、単なる技術論にとどまらず、地域の仕事や価値創出に焦点を当てた議論が展開されました。
イベントページ:https://techplay.jp/event/984388
セッション1:西海クリエイティブカンパニー 宮里 賢史 氏
株式会社西海クリエイティブカンパニーの宮里氏は、人口減少を前提とした社会でのビジネス展開について講演しました。同氏によれば、生成AIの登場により、データ形式を気にせずプロジェクトを始められるようになったとのこと。価値あるデータは専門的なものではなく、現場の資料や写真といった「目の前のデータ」にあり、これらをAIで活用することで専門知識にアクセスできると説明しました。
具体例として、長崎の水産業では、シール型データロガーで魚の輸送温度を記録・証明し、品質を付加価値に変換する取り組みを紹介。また、運送会社では、日々多数届く手書きFAX注文をAIで読み取り、受注から在庫確認、配送手配までを自動化するプロジェクトを展開中と報告しました。
宮里氏は最後に、身近なデータからビジネス価値を創出することが本質であり、今後はAIを効果的に活用する組織が長期的に成長すると結論づけました。
セッション2:オーシャンソリューションテクノロジー 国府田 諭 氏
オーシャンソリューションテクノロジー株式会社の国府田氏は、水産業に特化したデータ活用の取り組みを紹介しました。同社は漁業者支援サービス「トリトンの矛」を通じて漁船にIoT機器を設置し、GPSによる位置情報を自動記録しています。これにより従来手作業だった操業日誌が自動作成され、漁業者の負担が大幅に軽減されています。AIが航跡データから「漁獲努力量」(どこでどれだけ漁をしたか)を推定することで、水産資源の持続可能な管理に貢献しています。
石垣市での実証実験では、漁獲情報を衛星通信でリアルタイムに漁協へ送信し、仲買人への情報提供を迅速化。これにより魚価の向上と高付加価値化に成功した事例が報告されました。さらに、LPWA技術を活用した海難事故対策や、衛星データとAIによる赤潮予測など、多角的なアプローチも紹介されました。
セッション3:データサイエンティスト協会 内保 光太郎 氏
日本経済大学 講師でデータサイエンティスト協会 九州支部委員の内保氏は、「生成AIで変わるビジネス」と題し、AI技術の進化とビジネスへの影響を解説しました。同氏によれば、AIはマルチモーダル化やエージェント化へと進化し、将来的には業務プロセスを自律的に実行するアシスタントになると言及しています。特に、インターネット接続を必要としない「オンデバイスAI」は情報漏洩リスクを減らし、金融や医療分野での活用を促進すると述べました。
ビジネスへのAI導入では、単なるツール導入ではなく、業務プロセスの再設計が不可欠だと強調。AI導入を成功させる鍵は、目的と価値の明確な設定、そして客観的な評価指標とガバナンス体制の確立にあるとの見解を示しました。内保氏は最後に、実証実験(PoC)で終わらせず、組織への「定着」を目指すべきだと提言しました。
パネルディスカッション
パネルディスカッションでは、「長崎から見る、考えるデータ利活用」をテーマに議論が展開されました。長崎の課題について、「小規模だからこそ成功事例を作りやすい」とポジティブな側面を強調されました。一方で、補助金依存から脱却した自発的な取り組みの重要性と、エンジニアコミュニティの活性化が課題として指摘されました。企業のAI導入におけるセキュリティ懸念については、「リスクの低い社内業務からスモールスタートするべき」という実践的な提案がありました。
また「明日から何をすべきか」という問いに対しては、マインドセットの変革や、福岡などと比較して少ないIT勉強会などのコミュニティ活動の場を増やす必要性が共有され、活発な意見交換が行われました。
本イベントでは、長崎県内の先進的なAI・データ活用事例から今後のビジネス変革の展望まで、幅広い知見が共有されました。各セッションでは、現場の課題解決に直結する「目の前のデータ」の価値や、業界特化型DXの具体的アプローチが紹介されました。パネルディスカッションでは、長崎の小規模経済圏の持つ可能性と、それを活かすための自発的なコミュニティ形成の重要性が明らかになりました。このイベントは地方におけるデータ活用のリアルな現在地と、将来性を示す有意義なイベントとなりました。
今後も九州支部では、分析・DS・DXの実務に携わる方々を対象として、地方におけるデータサイエンスの普及と活用促進を目的にセミナーやイベントを継続的に開催してまいります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
データサイエンティスト協会 九州支部
株式会社TRAILBLAZER 田原卓弥 氏
- カテゴリ
-
-
DS関連NEWS
-
インタビュー
-
スキルアップ
-
コラム
-
教えて!DS
-
- アーカイブ
-
-
2026年
-
2025年
-
2024年
-
2023年
-
2022年
-
2021年
-
2020年
-
2019年
-
2018年
-
2017年
-
2016年
-
- 記事アクセスランキング
-
- タグ