2016.08.10
本は証明しながら読む ~日本統計学会会長・成蹊大学理工学部教授 岩崎先生インタビュー~
日本統計学会の会長を務めていらっしゃる、成蹊大学理工学部の岩崎先生。スキルチェックテストも、UPされるやいなや、早速チェックくださったそうです。今回は、先生がどのようにアナリティクスのスキルを獲得されてきたかを伺って来ました。
Q. 現在の主な研究内容をお聞かせください
岩崎: 現在、統計的な方法で因果関係を推論するというテーマで研究しています。昨今話題に上がるビッグデータとは対極で、すでに集まったデータをどう活用するのかを考えるのではなく、どのようにデータを集めるべきか等、理想的なやり方を探っています。例えば、薬の臨床試験において、どんなデータがあれば良いか事前にわかっていれば、うまく調査を進めることができると考えています。
Q. データ活用に携わるようになったきっかけをお聞かせください。
岩崎: 大学に入った当時、応用数学の3本柱の1つが統計学でした。ちょうど、お酒に関する官能評価に関わるチャンスがあり、人間の好みを扱う統計学が面白いと感じました。また、統計学は、コンピュータに関する知識、数学に関する知識の両方が必要なことから、いろいろなものに興味を持つことができました。
大学時代、FORTRANやBASICなどでプログラムを作成し、パンチカードを使って計算していたのは懐かしい思い出です。最近は、SASやSPSSなどのソフトウェアが浸透し、自分のデスクで処理が出来るようになりました。ソフトウェアの良い所は、データを入れれば、まず結果が出てくることだと思っています。もちろん、手法そのものを理解していくことは必要です。
分析を料理に例えて話すことがあるのですが、料理で言うレシピ(クックブック)のようなものがあっても良いと思っています。ただし、レシピ通り作ってもありきたりのものが出来るだけなので、おいしくするための工夫するところが腕の見せ所です。多変量解析を例にとると、コンピュータが出してくれる有望な変数の中からどの変数を説明変数として選ぶかや、線形だけではなく非線形でモデリングするかなどが、工夫ポイントです。
Q. データ活用に携わるに際して、どのようなことを心がけていらっしゃいますか?
データサイエンティスト協会が定義している、データサイエンス力、データエンジニアリング力、ビジネス力の3つすべてを一人で身に付けることは難しいと考えています。それぞれの専門性を持ったメンバがGive & Takeでお互いに評価しながらプロジェクトを進めて行くのが良いと思います。各メンバが専門性を発揮し、うまくいった事例として、C型肝炎に関するプロジェクトがあります。医者の持つ知識と、統計学者の持つ知識がうまく融合し、治療方法を研究することができました。このプロジェクトでは、データエンジニアリング部分を担う計算のコンサルタントを入れたのもポイントでした。
Q. スキルを習得されるに際して、どのようなことを行われたか、工夫したことや苦慮したことなど、何かエピソードがございましたらお聞かせください。
岩崎: スキルを習得するために、統計学の本を読んで勉強すると思いますが、本を眺めているだけでは知識が身に付きません。本は眺めるのではなく、本に書いてあることを証明しながら読む必要があります。可能であれば、いろいろな文献を読み、複数の観点から検討することが出来るようになれば理解が深まります。学生には、きちんと本に書いている内容を証明するように指導しています。結局、最後は自分でやらないとダメということです。

スキル委員 孝忠・原茂
Q. ご専門領域の今後の発展性/方向性/新たな活用の領域に関するアイデアなどがございましたらお聞かせください。
岩崎: これまで統計学がやってきたことは継続していくとして、時代にあった具体的なデータの扱い方を研究していくことも必要だと考えています。例えば、欠測データをどう扱うかということについても、まだ研究途上の分野と考えています。医療分野では欠測データを扱うことがありますが、マーケティング分野にも欠測データがあるはずで、今後検討対象となるはずです。また、テキストデータや画像データなど、数値だけではないデータをどう扱っていくかは、今後のテーマだと思っています。
Q. 先生が考えられるデータプロフェッショナル・データサイエンティストを目指す方に高めて欲しいスキルやマインド、その他メッセージがございましたらお願いいたします。
まずは、コンピュータに対する知識、統計学の知識を身に付けることが必要だと考えています。コンピュータについては実践すること、統計学については方法論に対する理論を理解することが重要だと思います。可能であれば、統計学の手法の歴史を知っておくと非常に良いです。ビジネス力やコミュニケーション力は追々身について行くものなので、まずは、コンピュータおよび統計学の2つを磨いて頂きたいです。
データサイエンティスト協会のスキルチェックリストで言うと、見習いレベル(★)は、すべての学生に身に付けて欲しい内容だと思っています。独り立ちレベル(★★)は、大学卒業時には身に付けておいて欲しいと思っています。棟梁レベル(★★★)は、大学の外で身に付けるような内容なので、社会人になってから修得していくのが良いと思います。
また、最近海外のシンポジウムに参加する機会があったのですが、日本人は英語力が足りないと痛切に感じました。次のステージに進みたい、自分を高めたいと考えている人は、是非、語学も磨いて頂きたいと思います。
———————————————————————————-
取材日:2016/07/04(月)13:00~14:20
取材メンバ:孝忠、原茂、菅
———————————————————————————-
編集後記

スキル委員:原茂
ExcelやSASにいろいろ突っ込めば、結果がぱっ!と出てくるありがたみを感じつつ、手法に対する理解も深めていきたいと思いました。がんばります。

スキル委員:菅
「本は証明しながら読む」というメッセージ、たいへん印象的でした。また、最後におっしゃられていた「英語力」についても、私自身課題に感じているスキルでしたので、先生のお言葉を思い出しながら高めて行きたいと思っています。
- カテゴリ
-
-
DS関連NEWS
-
インタビュー
-
スキルアップ
-
コラム
-
教えて!DS
-
- アーカイブ
-
-
2025年
-
2024年
-
2023年
-
2022年
-
2021年
-
2020年
-
2019年
-
2018年
-
2017年
-
2016年
-
- 記事アクセスランキング
-
- タグ
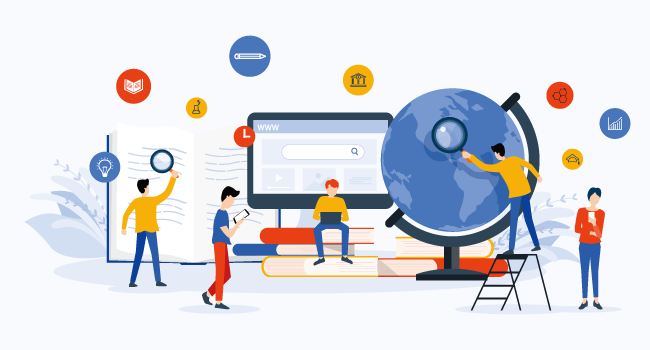




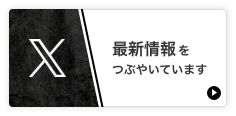
スキル委員:孝忠
岩崎先生のお言葉を受け、ぼ~っと本を眺めているだけの自分を反省しました。これからは証明しながら本を読む癖をつけなければ…